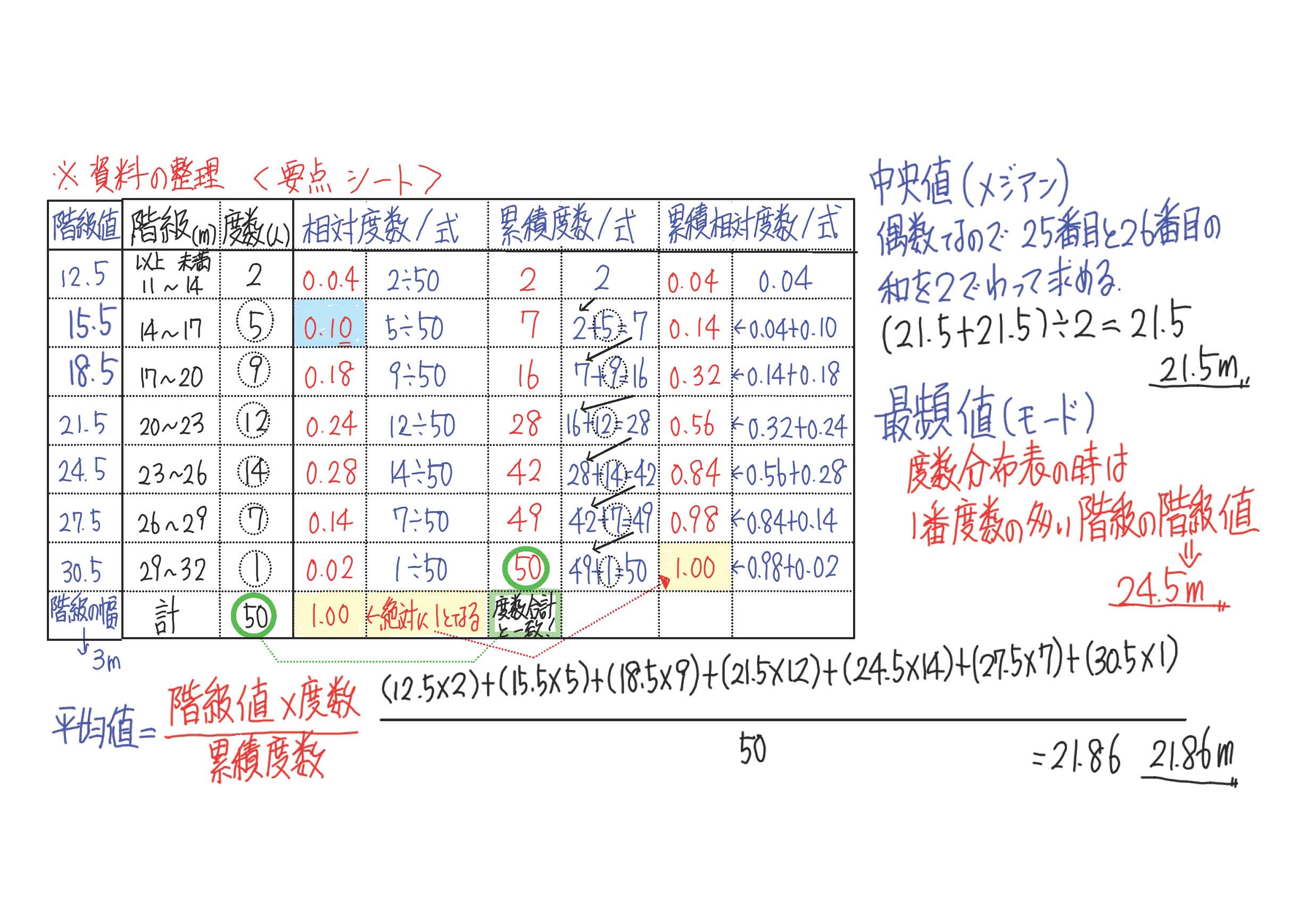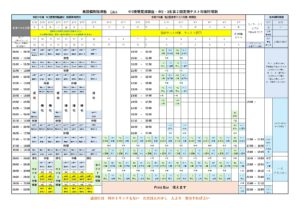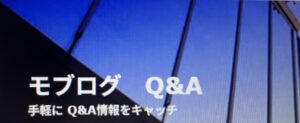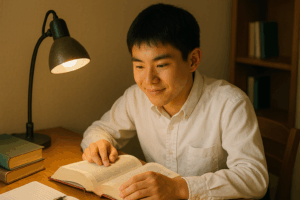前稿までに当塾のプリント制作を担う
5つの基幹ソフトをご紹介しました。
本稿では、これらのソフトにより作成
されるプリントと共に、私自身が作成
するプリントの種類と想いをご説明し
ていきたいと思います。
1つめにご説明するプリントは、通常
の学習プリントのイメージとは少し異
なるものとなります。それは・・・
【授業板書プリント】です。
当塾では、新規開塾以前に作成し保存
されていた板書PDFは基本的にすべて
使用しないことに致しました。それは
下記に述べる 生徒さんが使いやすく
学習効果が実感できる板書ノートへ移
行するために全面刷新するためです。
そしてその改革は授業自体の在り方や
その後の PrintBar での各生徒さんご
との演習の仕組み、また自宅課題の内
容など、全ての見直しにつながってい
ます。以下、実際の授業板書プリント
にそってご説明をさせて頂きます。
※下記の画像は、授業時点で電子黒板に表示さ
れています。私が授業前に予め作成しています。
[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/241293b6085f32224eeb38d5bc465904.pdf”]
まずこの板書は、今日自分たちが学び解けるよ
うになる学習内容を示しています(青字部分)
同時に、教室内のプリンターからその場でフル
カラー印刷され配布されています。
⬇
次に今回は基本的な事項は履修済みでしたので
配布したプリントに直接書き込んで解いてみよ
うと声かけをして取り組んでもらいました。
その際に7項目ある青字部分の内、階級値・
相対度数・累積度数・累積相対度数の4つだけ
を解くことと、間違えてもいいから計算した式
を残すことを注意する様に伝えています。
⬇
[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/6a52ae519db1b2e6fce5d7dc9f29f9e8.pdf”]
演習時間を終え、解説の時間となる時点で、こ
の板書に切り替わります。この際に、具体的な
解法に使用した式は、一切省略せずに書き記す
ことを当塾では大切にしています。そして生徒
さんにも、必ず式を残すように指導しています
⬇
次に7項目ある青字部分の内、残っている3項
目、平均値・中央値・最頻値について、解いて
みるように声かけをしました。
⬇
[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/12fba2244b06137bc726b5f29e610af5.pdf”]
演習を終えた生徒さんにお見せする3枚目の板
書がこちらになります。
ここでお気づき頂けるかと思いますが、先ほど
の2枚目の板書を縮小し、残る3項目の説明が
1枚のPDFに納められています。これが電子黒
板で授業することの利便性の1つです。
つまり・・・
1枚目の問題用紙で学ぶべき事項を確認し
2枚目の解説で4項目事項の解法を確認し
3枚目の解説で解法の全体像を確認する
生徒さんには、この授業の流れの中で同時
進行で、1枚目から3枚目のフルカラー印
刷された【授業板書プリント】が配布され、
手元で確認しながら私の解説を聞くことと
なります。
その際に、多くの学習事項を1枚に《てん
こ盛り》にした要点プリントをもらうので
はなく、ステップごとに理解を確認してい
けるプリント。それは言い換えるなら、授
業展開に時系列的に対応した板書プリント
が配布されるのです。
これにより、後半に移行するPrintBarで、
自分が何をすべきかが生徒さんには明確に
なっていきます。
説明が長くなりました。この続きは次稿で
ご説明させて頂きます。