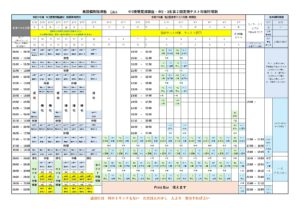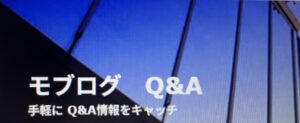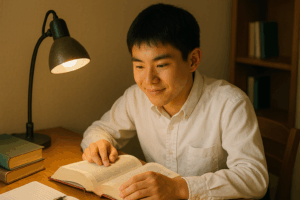2回の連続投稿で、前編・中編と配信してきました
足し算から割り算の発想についての投稿ですが、
本日で最終となります。前回の投稿で、日数と科目
について、おおざっぱに考えることの危険性につい
てお話しましたね。今日は実際の計画を立てる方法
について説明したいと思います
まず大切なことは、前回も書かせてもらいましたが
1日最低でも3科目はしないと、まったく間に合わ
ないということ。
次に大切なことは、その3科目の学習時間は、同じ
である必要はないということです。そして、もう1
つ大切なことは、嫌いな科目やしたくない学習は、
一番体力がある時に、短い時間で
先に先に!終えるということです
https://qanda2025.blog/wp-content/uploads/2025/05/時間割作成例(14日3科目版).jpg
上の具体例を見てみて下さい。
この表は2週間14日間の学習計画の1例です。
ポイントは、英語が苦手だと仮定して、
学習時間は25分・35分・50分としました。
この表の上から下という順番でしてもいいし、
英語はその日の最初に指定された時間で学習を
しても構いません。ここで気づいて欲しいことは
13日間で英語がない日は3日だけという点です
苦手な科目は基本的に毎日学習することが大切で
でもさすがに途中でない日も作らないと気持ちが
折れるので、そこも工夫する。また短い時間の日
と2番目に長い時間の日に分けていくことなど、
少しでも自分が頑張れるようにアレンジすること
が、とても大切なのです。
そして、何よりも大切なことは、計画は自分で
想いを込めて作らない限り、何の意味もないし
絶対に続かないし効果も出ないということです。
最後に、この表を見て分かることは、実際に、
科目ごとの時間と回数を入れてみたら、2週間で
できる学習時間がおおざっぱに想像している程は
多くないことにですよね。そもそも、次回の定期
テストは8科目~9科目ですよ
だから2週間前からでは、
絶対に間に合わないのです
授業で詳しくお伝えしますが4週間前
から2週間前までの短め学習と、
2週間前から当日までのぶっちぎり計画
を皆さんと相談しながら、
本年度は毎回決めていきたいと思います